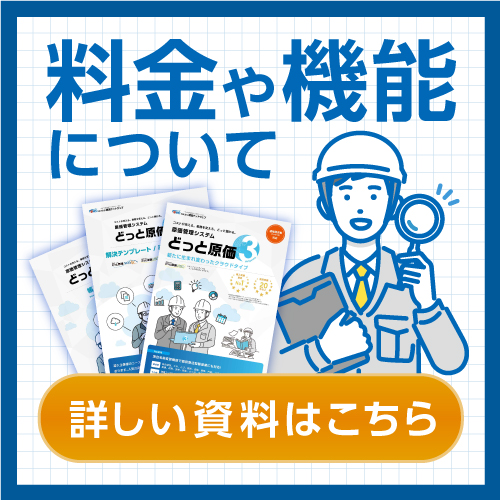【完全版】「労務費」「法定福利費」「安全衛生経費」の見積もりガイド|内訳・計算・注意点を徹底解説
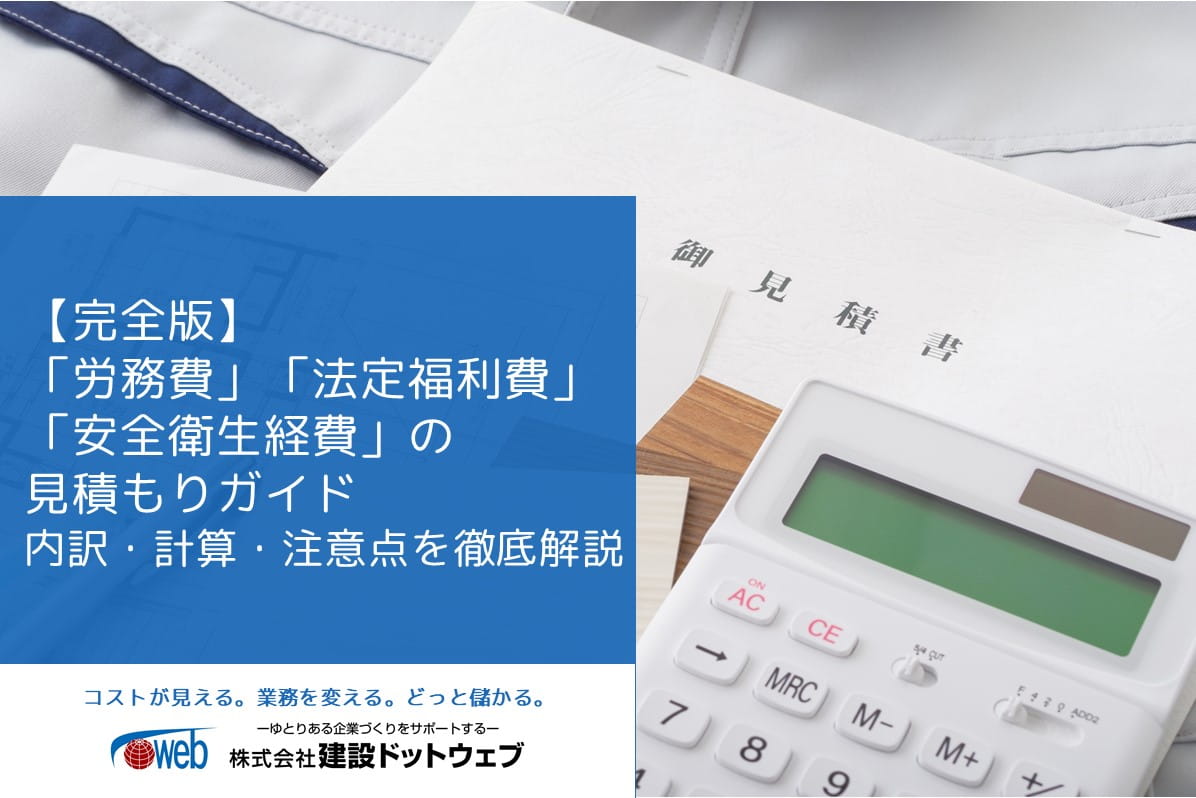
建設工事の見積もりにおいて、「労務費」「法定福利費」「安全衛生経費」は、適正な工事価格を算定し、事業を健全に運営していく上で極めて重要な要素です。しかし、これらの経費が十分に理解されないまま、あるいは意図的に過少に見積もられるケースが後を絶ちません。
建設業界の課題|不適切な見積もりによる弊害とは?
不適切な見積もり、特に労務費等の過少計上は、単に「安く工事を受注できる」という問題ではありません。それは、建設業界全体が抱える構造的な課題と深く結びついています。
労働者の処遇悪化、建設業の衰退リスク
下請業者に適正な対価が支払われなければ、そのしわ寄せは必然的に現場で働く労働者に向かいます。賃金の抑制、長時間労働の常態化、社会保険への未加入といった問題は、労働者の生活を脅かし、建設業から人材が離れていく大きな原因となります。
結果として、担い手不足がさらに深刻化し、技術・技能の承継も困難になり、建設業全体の活力が失われるリスクがあります。
この記事で分かること:3つの経費の正しい知識と見積もり方法
このような状況を改善し、建設業が持続可能な産業であり続けるためには、建設事業に携わる一人ひとりが、工事に必要な経費、特に「人」に関わるコストを正しく理解し、適正に見積もりに反映させることが不可欠です。
この記事では、以下の3つの重要な経費について、その内訳から計算方法、見積もり時の注意点までを徹底的に解説します。
- 労務費:現場で働く人々の対価
- 法定福利費:法律で定められた社会保険料(事業主負担分)
- 安全衛生経費:労働者の安全と健康を守るための費用
さらに、これらの経費を適切に見積書に反映させるための「標準見積書」の活用方法や、元請・下請・発注者それぞれの役割についても解説します。
労務費の内訳と計算
まず、建設工事の根幹をなす「労務費」について見ていきましょう。
労務費とは?
労務費とは、建設工事の施工に直接または間接的に従事する労働者に対して支払われる賃金、給料、手当などの総称です。工事原価の中でも大きな割合を占める重要な費用項目です。
労務費の内訳
労務費は、大きく「直接労務費」と「間接労務費」に分けられます。
直接労務費
工事現場で、建設物の制作や組み立て、施工などの直接的な作業に従事する技能労働者(職人、作業員など)に支払われる賃金です。日給や時間給で計算されることが多いです。
間接労務費
工事現場には直接従事しないものの、工事の施工に必要な業務を行う従業員に支払われる費用です。
- 現場監督や現場事務員などの給与・手当
- 労務管理に要する費用
- 従業員の賞与・退職金の引当金繰入額など
見積もりにおいては、特に直接労務費を正確に算出することが重要ですが、間接労務費も工事原価の一部として適切に考慮する必要があります。
労務費の計算方法
直接労務費は、一般的に以下の式で計算されます。
直接労務費=労務単価×所要人数(工数)
- 労務単価:
技能労働者一人一日あたり、または一時間あたりの賃金単価です。公共工事では「公共工事設計労務単価」が基準となりますが、民間工事では、自社の賃金規定や地域の賃金相場、労働者の経験・スキルなどを考慮して設定します。 - 所要人数(工数):
その工事を完成させるために必要な延べ作業員数(人日:にんにち)または延べ作業時間数です。設計図書や仕様書、過去の類似工事の実績などから算出します。
割増賃金の考慮
時間外労働、休日労働、深夜労働が発生した場合には、労働基準法に基づき割増賃金を支払う必要があります。見積もり段階でこれらの発生が見込まれる場合は、割増分も労務費に含めて計上しなければなりません。安易に割増分を計上しないことは、法令違反のリスクや、実際に発生した場合の赤字リスクにつながります。
法定福利費との関係
労務費(賃金)は、後述する健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの法定福利費(社会保険料)を計算する際の基礎となります。労務費を過少に見積もることは、結果的に法定福利費の計上漏れにもつながる可能性があるため注意が必要です。
見積もり時の注意点
- 過少見積もりのリスク:
労務費を不当に低く見積もることは、労働者の処遇悪化を招くだけでなく、建設業法で禁止されている「不当に低い請負代金の禁止」に抵触する恐れがあります。 - 標準労務費の活用:
令和6年の建設業法改正で導入された「標準労務費」は、適正な労務費水準の目安となります。見積もり作成や価格交渉の際に参考にしましょう。 - 標準見積書への記載:
国土交通省が推奨する「標準見積書」には、労務費の内訳を明示する欄があります。根拠のある労務費を算出し、適切に記載することが、元請や発注者に対する説明責任を果たす上で重要です。
法定福利費の種類と計算
次に、従業員を雇用する上で事業主が負担すべき「法定福利費」について解説します。これは法律で加入が義務付けられている社会保険料等のうち、事業主が負担する部分を指します。
法定福利費とは?
法定福利費は、労働者の生活保障や万が一の際のセーフティネットとして不可欠な費用であり、企業の規模や業種に関わらず、加入要件を満たす従業員がいれば必ず発生します。見積もりにおいて、この法定福利費を必要経費として正確に計上することは、企業の法令遵守と労働者の福祉のために極めて重要です。
法定福利費の種類
主な法定福利費には以下のものがあります。
健康保険
従業員やその家族が病気やけがをした際の医療費負担を軽減するための保険です。保険料は事業主と従業員で半分ずつ負担します。(協会けんぽ、組合健保など)
厚生年金保険
従業員の老後の生活保障(老齢年金)や、障害・死亡に対する保障(障害年金・遺族年金)のための保険です。保険料は事業主と従業員で半分ずつ負担します。
雇用保険
従業員が失業した場合の生活保障(失業給付)や、育児・介護休業中の給付、能力開発支援などを行う保険です。保険料は事業主と従業員で負担しますが、事業の種類によって負担割合が異なります。建設業は一般の事業とは異なる料率が適用される場合があります。
労災保険(労働者災害補償保険)
従業員が業務中や通勤中にけが、病気、死亡した場合に、治療費や休業補償などを給付する保険です。保険料は全額事業主が負担します。保険料率は事業の種類によって異なります。
その他(子ども・子育て拠出金など)
厚生年金保険の適用事業主が負担するもので、地域の子育て支援などに充てられます。保険料は全額事業主が負担します。
法定福利費の計算方法
法定福利費(事業主負担分)は、一般的に以下の計算式で求められます。
法定福利費(事業主負担分)=対象となる賃金総額×各保険料率×事業主負担割合
- 対象となる賃金総額:
各保険料の計算基礎となる賃金(基本給、手当など)の総額です。保険の種類によって対象となる賃金の範囲が若干異なる場合があります。 - 各保険料率:
健康保険料率、厚生年金保険料率、雇用保険料率、労災保険料率、子ども・子育て拠出金率など。これらの料率は、毎年のように改定されるため、常に最新の情報を確認する必要があります。都道府県や加入している健康保険組合によっても料率が異なる場合があります。 - 事業主負担割合:
各保険制度で定められた事業主の負担割合です。(例:健康保険・厚生年金は原則1/2、労災保険・子ども子育て拠出金は全額)
※注意:保険料率は頻繁に改定されます。見積もり・積算時には、必ず日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)、厚生労働省などの公式サイトで最新の保険料率を確認してください。
- 日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
- 厚生労働省(雇用保険・労災保険):https://www.mhlw.go.jp/
見積もり時の注意点
- 計上漏れのリスク:
法定福利費は法律で定められた必要経費です。見積もりへの計上漏れは、法令違反となるだけでなく、後から不足分を負担することになり、企業の経営を圧迫します。特に下請業者においては、元請から法定福利費相当額が支払われないと、労働者の保険料納付にも支障をきたす恐れがあります。 - 標準見積書への記載:
標準見積書には「法定福利費」を明示する欄が設けられています。労務費とは別に、根拠を持って算出した法定福利費(事業主負担分)を正確に記載しましょう。これにより、元請や発注者に対して、必要な費用であることを明確に示すことができます。
安全衛生経費を正しく理解する
労働者の安全と健康を守ることは、企業の最も重要な責務の一つです。そのために必要な「安全衛生経費」も、見積もりに適切に反映させる必要があります。
安全衛生経費とは?
安全衛生経費とは、建設現場における労働災害を防止し、労働者が安全かつ健康に働くことができる環境を整備するために必要な費用の総称です。労働安全衛生法等で実施が義務付けられている対策費用も含まれます。
安全衛生経費の内訳
安全衛生経費には、主に以下のようなものが含まれます。
安全対策費
- 仮設関係:
足場、安全通路、手すり、安全ネット、型枠支保工などの設置・点検・補修費用。 - 安全施設・設備:
墜落防止設備、飛来落下防止設備、安全標識、消火設備、避難誘導灯などの設置・維持管理費用。 - 保護具等:
ヘルメット、安全帯、安全靴、保護メガネ、防じん・防毒マスクなどの購入・管理費用。 - 安全教育・訓練:
新規入場者教育、職長教育、特別教育、技能講習などの実施費用、KY活動(危険予知活動)関連費用。 - 安全管理体制:
安全管理者の選任、安全パトロール、安全協議会の運営などにかかる費用。
健康管理費
- 健康診断:
雇入時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断などの実施費用。 - 作業環境測定:
粉じん、騒音、有機溶剤などの作業環境測定費用。 - 衛生対策:
熱中症対策(休憩所、飲料水)、感染症対策(消毒液、マスク)、救急用具の整備費用。
・健康相談・メンタルヘルス対策に関する費用。
その他
安全衛生に関する書類作成費用、保険料(法定外の労災上乗せ保険など)など。
安全衛生経費の計算方法
安全衛生経費は、工事の種類、規模、現場の状況、工期、適用される法令などによって必要な対策や費用が大きく異なります。そのため、労務費や法定福利費のように特定の料率で計算することは困難です。
一般的には、以下の方法で算出します。
必要な安全衛生活動の洗い出し:当該工事において、法令で義務付けられている事項や、現場のリスクアセスメントに基づいて必要となる安全衛生対策を具体的にリストアップします。
- 費用の積算
洗い出した各対策項目について、必要な資機材の費用、人件費、外部委託費などを積み上げて計算します。過去の類似工事の実績や、国土交通省の「共通仮設費積算基準」などを参考にすることも有効です。
見積もり時の注意点
安全衛生経費は、労働者の生命と健康を守るためのコストであり、安易に削減することは絶対に避けなければなりません。事故が発生した場合の損失(人的・物的損害、補償、社会的信用の失墜など)は計り知れません。
- 必要性の説明:
見積もり提出時や価格交渉において、計上した安全衛生経費が、法令遵守や労働災害防止のために不可欠であることを具体的に説明できるように準備しておくことが重要です。 - 標準見積書への記載:
標準見積書では、安全衛生経費は「共通仮設費」や「現場管理費」の中に含まれることが多いですが、その内訳として意識し、必要な費用を漏れなく計上することが求められます。可能であれば、別途内訳として明示することも有効です。
標準見積書の活用
これまで見てきた労務費、法定福利費、安全衛生経費などを適正に見積もりに反映させ、元請や発注者に理解を得るために有効なツールが、国土交通省が推奨する「標準見積書」です。
標準見積書のメリット
- 見積もりの透明性向上:
工事価格の内訳が明確になり、どこにどれだけの費用がかかっているのかが分かりやすくなります。 - 価格交渉の円滑化:
労務費や法定福利費といった、本来削減すべきでない費用が明示されることで、根拠のない値引き要求を防ぎ、建設的な価格交渉が可能になります。 - 適正な価格での契約促進:
必要な経費が適切に計上されていることを示しやすくなり、適正な価格での契約締結につながります。
標準見積書の記載例(労務費、法定福利費、安全衛生経費の部分)
(ここに標準見積書の様式イメージと、労務費、法定福利費、現場管理費(安全費等を含む)などの項目にどのように金額を記載するかの簡単な説明・ポイントを記載)
例:「労務費」欄には、直接労務費を工種別に記載。「法定福利費」欄には、算出した事業主負担額を明記。「現場管理費」の内訳として安全費(安全衛生経費相当分)を考慮していることを示す、など。
例(https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/50148/)
標準見積書作成時の注意点
- 最新様式の使用:必ず国土交通省が提示している最新の標準見積書様式を使用しましょう。
- 根拠のある積算:各項目には、これまで説明したような根拠に基づいた金額を記載します。
- 内訳の明確化:特に労務費や現場管理費については、可能な範囲で内訳(職種別単価、安全対策費の内訳など)を補足資料として添付すると、より説得力が増します。
元請・下請・発注者の役割と責任
適正な見積もりと契約を実現するためには、建設工事に関わるそれぞれの立場が役割と責任を果たす必要があります。
元請業者の役割と責任
- 下請業者への適正な見積もり依頼:
工事内容や工程、必要な経費の内訳(特に労務費)を可能な限り明示して見積もりを依頼する。 - 標準見積書の活用推奨・指導:
下請業者に対して標準見積書の使用を推奨し、作成方法について必要に応じて指導する。 - 適正な価格での契約:
下請業者から提出された見積もりを尊重し、標準労務費などを参考に、労務費や法定福利費が適切に確保された価格で契約する。不当な値引き要求は行わない。 - 契約内容の書面化:
合意した内容を契約書として明確に残す。
下請業者の役割と責任
- 適正な見積もりの作成:
労務費、法定福利費、安全衛生経費などを漏れなく正確に積算し、標準見積書を用いて提出する。 - 元請業者との交渉:
見積もりの根拠を明確に説明し、必要な費用が確保できるよう、元請業者と対等な立場で交渉する。 - 情報収集:
標準労務費、最新の保険料率、関連法規などの情報を常に収集し、知識をアップデートする。
発注者(民間・公共)の役割と責任
- 適正な価格での発注:
建設業者が適正な利益を確保し、労働者の処遇改善や安全対策を実施できるよう、極端な低価格での発注は避ける。 - 標準見積書の理解:
提出された標準見積書の内容を理解し、労務費や法定福利費などが適切に計上されているかを確認する。 - 建設業法・下請法の遵守:
優越的な地位を利用した不当な要求(不当な値引き、追加工事の無償強要など)は行わない。
適正な見積もりで建設業の未来を築く
建設工事における適正な見積もりは、単なる金額計算ではありません。それは、現場で働く人々の生活を守り、安全を確保し、高品質な建設物を提供するための基盤であり、建設業の未来を左右する重要な取り組みです。
今回のポイント再確認
- 労務費・法定福利費・安全衛生経費は、建設事業に不可欠なコストであり、正確な理解と計上が必要。
- 標準見積書は、適正な価格形成と透明性確保のための有効なツール。
- 元請・下請・発注者それぞれの協力により、公正な取引環境を構築することが重要。
私たち建設ドットウェブは、建設業に携わる皆様が、これらの重要な経費を正しく理解し、自信を持って適正な見積もりを作成・提出できるよう、情報提供やノウハウ共有に努めてまいります。また、見積もり業務の効率化を支援するシステムの提供などを通じて、皆様の事業運営をサポートいたします。
適正な見積もりと契約を通じて、労働者が安心して働ける環境を整備し、建設業が社会から信頼され、魅力ある産業として発展していく未来を、共に築いていきましょう。