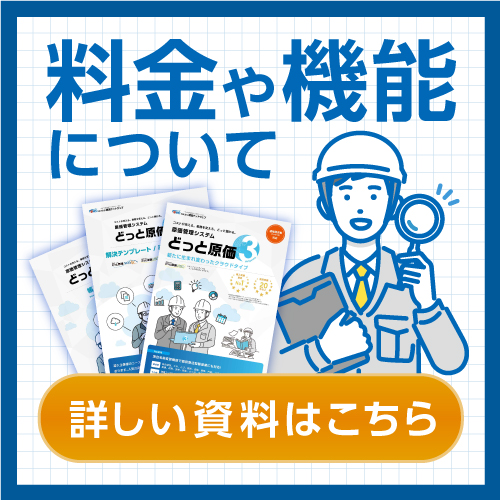【事例で解説】建設Gメンは何をチェックする?「標準労務費」「原価割れ契約」違反の実態と対策
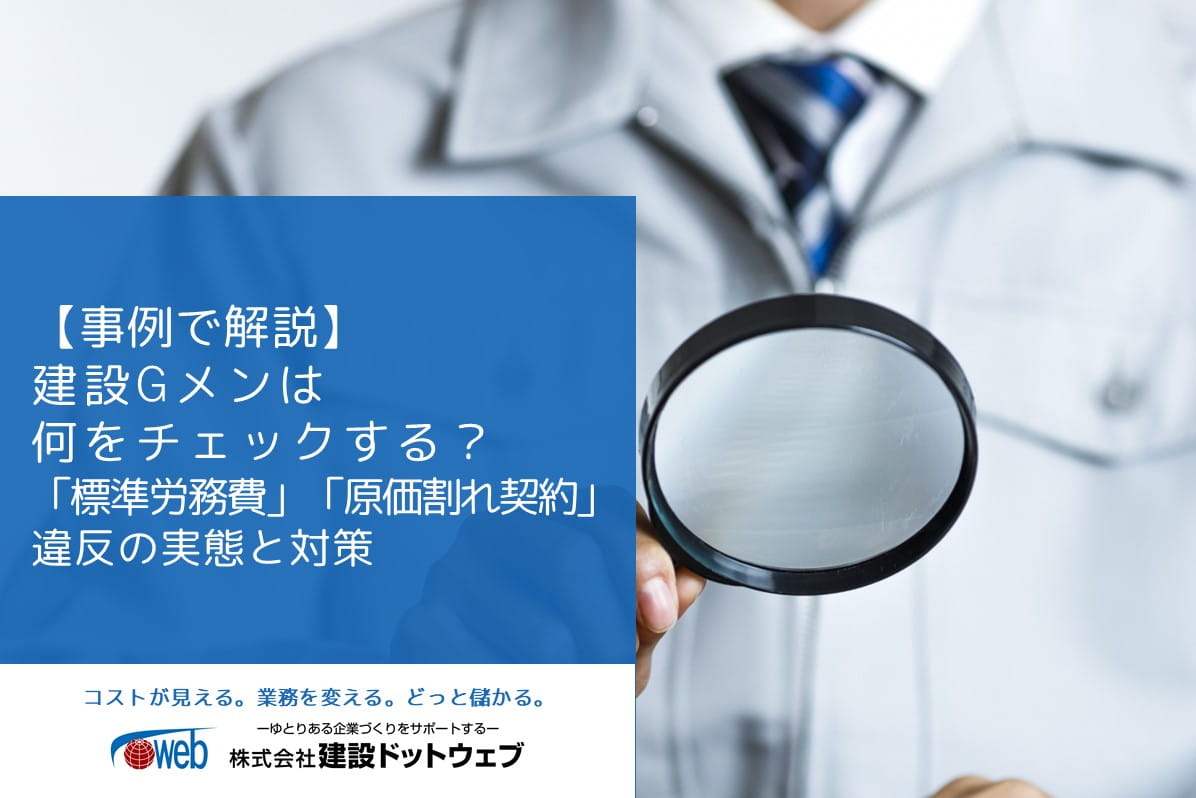
建設業界では、長年にわたり、労務費のダンピング(不当な値引き)や原価を無視した低価格での契約といった問題が指摘されてきました。これらの不適切な取引は、現場で働く方々の処遇を悪化させるだけでなく、工事の品質低下や安全性の軽視にもつながり、建設業全体の持続可能性を脅かす深刻な課題となっています。
目次
建設業界の課題|不当な低価格競争の蔓延
資材価格が高騰する中でも、依然として厳しい価格競争が存在し、そのしわ寄せが下請業者や労働者に向かいやすい構造があります。特に労務費は、目に見えにくいコストであるためか、削減の対象とされやすい傾向がありました。
労働者へのしわ寄せ、品質低下のリスク
不当な低価格受注は、下請業者に適正な対価が支払われない状況を生み、結果として労働者の賃金抑制や長時間労働につながります。これは担い手不足を加速させるだけでなく、必要な安全対策の省略や手抜き工事を誘発し、建設物・インフラの品質や安全性を損なうリスクもはらんでいます。
この記事で分かること
このような状況を改善するため、国は「担い手3法」の改正等を通じて対策を強化しています。この記事では、以下の点について、事例も交えながら具体的に解説します。
- 適正な労務費の目安となる「標準労務費」
- 「原価割れ契約禁止」のルールと違反となるケース
- 不適切取引を取り締まる「建設Gメン」の役割と調査内容
- 違反した場合のペナルティとその影響
- 建設事業者が取るべき具体的な対策
「標準労務費」とは?適正な労務費の目安
「標準労務費」は、令和6年の建設業法改正で導入された考え方で、建設工事に従事する労働者の標準的な賃金水準を示すものです。国土交通大臣が公共工事設計労務単価などを参考に作成し、関係者に確保を勧告できるようになります。目的は、労務費のダンピングを防ぎ、労働者に適正な賃金が支払われる環境を整備することです。
標準労務費の算出方法
公共工事設計労務単価をベースに、社会保険料の事業主負担分や地域の実情などを考慮して算出される見込みです。具体的な内容は今後のガイドライン等で示されます。
原価割れ契約禁止|何が違反になるのか?
建設業法では、「不当に低い請負代金の禁止」(第19条の3)が定められています。いわゆる「原価割れ契約」そのものを直接禁止する条文ではありませんが、実質的に原価を著しく下回るような不当な契約を規制するものです。
原価割れ契約とは?
工事を完成するために通常必要とされる費用(労務費、材料費、経費など)を下回る金額で契約することです。
建設業法における原価割れ契約の禁止
建設業法第19条の3では、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常の原価を著しく下回る請負代金で契約を強いることを禁止しています。
令和6年の改正では、特に「労務費相当額」について、元請負人に著しく低い見積もりや契約をしないよう配慮する努力義務が課され、標準労務費が「通常の原価」を判断する目安の一つとなることが期待されています。
違反となるケース、ならないケース(事例で解説)
どのような場合に「不当に低い請負代金」と判断される可能性があるのか、具体的なケースを見てみましょう。(※これらは一般的な考え方であり、個別の事案ごとに判断されます)
ケース1:資材価格の高騰を見込まず、極端に低い労務費で見積もりを作成した場合
- 状況:
最近の資材価格高騰を考慮せず、標準労務費も大幅に下回るような労務費で下請業者に見積もりを作成させ、契約した場合。 - 判断:
「通常の原価」を著しく下回る可能性が高く、元請負人の地位を不当に利用していると認められれば、建設業法違反となる可能性が高いと考えられます。
ケース2:公共工事で、予定価格を大幅に下回る金額で入札した場合
- 状況:
公共工事の入札で、予定価格や調査基準価格を大幅に下回る金額で落札した場合。 - 判断:
低入札価格調査の対象となり、適正な履行が確保できないと判断されれば契約できない場合があります。また、その契約金額が通常の原価を著しく下回り、下請業者にしわ寄せが及ぶような場合は、建設業法違反(不当に低い請負代金の禁止)に問われる可能性もゼロではありません。
ケース3:赤字覚悟で受注したが、結果的に適正な労務費を支払えた場合
- 状況:
経営戦略上、一時的に赤字覚悟で受注したが、自社の持ち出し等により、下請業者には標準労務費等を踏まえた適正な代金を支払い、労働者の処遇にも問題がなかった場合。 - 判断:
結果的に下請業者や労働者へのしわ寄せが発生していなければ、直ちに建設業法違反とはならない可能性もあります。しかし、原価割れ受注は経営を圧迫し、将来的に問題を引き起こすリスクがあるため、推奨される行為ではありません。
発注者側の責任と注意点
「不当に低い請負代金の禁止」は主に元請負人を対象とした規制ですが、発注者(特に民間発注者)も無関係ではありません。
- 下請法との関係:
発注者が優越的な地位を利用して、不当に低い価格で建設業者に工事を発注した場合、下請法違反(買いたたきなど)に該当する可能性があります。 - 社会的責任:
適正な価格での発注は、建設業の担い手確保や品質確保につながり、ひいては社会全体の利益となります。発注者にも、サプライチェーン全体での適正な取引慣行を推進する社会的責任があると言えます。
建設Gメン徹底解剖|その役割と活動内容
不適切な取引慣行を是正し、法令遵守を促すために、国土交通省は「建設Gメン」による監視体制を強化しています。
建設Gメンとは?(設置目的、組織体制)
建設業における不適切な重層下請構造や、労務費・下請代金のダンピング、社会保険未加入といった問題に対し、集中的かつ機動的な調査・指導を行うために設置されました。
国土交通省本省および各地方整備局等に配置されており、建設業の法令や実務に精通した職員が担当しています。
建設Gメンの役割(調査、指導、勧告・公表など)
建設Gメンは、以下のような役割を担っています。
- 実態調査:
建設現場への立入検査や、元請・下請業者へのヒアリング、関係書類の確認などを通じて、取引の実態を調査します。 - 法令違反の指導:
調査の結果、建設業法等の法令違反が疑われる場合には、是正指導を行います。 - 悪質業者への対応:
指導に従わない、または違反が悪質・常習的な場合には、建設業法に基づく監督処分(指示、営業停止など)や、勧告・公表といった措置につなげます。 - 情報収集・分析:
現場の実態や問題点を収集・分析し、制度改善や政策立案に役立てます。
建設Gメンの調査方法
建設Gメンは、様々な方法で調査を行います。
- 立入検査:
事前の通知なく、建設現場や営業所に立ち入り、帳簿書類(契約書、注文書、請求書、賃金台帳など)の確認や、関係者への聞き取り調査を行います。 - ヒアリング:
元請業者、下請業者、労働者など、関係者から個別に事情を聞き取ります。
資料提出要求:必要に応じて、契約関係書類、施工体制台帳、賃金支払いに関する資料などの提出を求めます。 - 通報制度の活用:
建設業に関する法令違反や不適切な取引に関する情報提供(通報)も、調査の端緒となります。(国土交通省や地方整備局には通報窓口が設置されています)
建設Gメンによる摘発事例
(※以下は、報道等で想定される一般的な事例です。実際の摘発事例の詳細は、国土交通省の発表等をご確認ください。)
建設Gメンの調査により、以下のような事例が指摘・指導されるケースが考えられます。
- 事例A(労務費ダンピング):
元請業者が、標準労務費を大幅に下回る金額で下請業者に工事を発注し、下請業者が労働者に適正な賃金を支払えていなかった。 - 事例B(不適切な見積もり):
元請業者が、下請業者に対し、労務費などの内訳を明示せずに一方的に低い金額で見積もりを提出させ、契約していた。 - 事例C(偽装一人親方):
実質的には雇用関係にある労働者を、形式的に一人親方として扱い、社会保険料等の負担を逃れていた。 - 事例D(不適切な再下請):
施工体制台帳に記載のない業者に、無許可で工事を丸投げしていた。
違反した場合のペナルティとは?勧告・公表の影響
建設業法に違反した場合、特に「不当に低い請負代金の禁止」などに違反し、勧告・公表措置が取られた場合、企業には大きな影響が及びます。
国土交通大臣による勧告・公表
建設業法違反が認められ、是正指導にも従わない場合など、国土交通大臣(または都道府県知事)は、事業者に対して必要な措置を取るよう「勧告」することができます。
さらに、正当な理由なく勧告に従わない場合には、その事実(企業名、違反内容、勧告内容など)を「公表」することができます。
企業への影響(風評被害、入札への影響など)
勧告・公表が行われると、以下のような深刻な影響を受ける可能性があります。
- 社会的信用の失墜・風評被害:
企業名が公表されることで、「法令違反企業」「ブラック企業」といったネガティブなイメージが広がり、社会的信用が大きく損なわれます。 - 受注への影響(特に入札):
公共工事の入札において、指名停止措置を受ける可能性が高まります。民間工事においても、取引先からの信頼を失い、受注機会が減少する恐れがあります。 - 金融機関からの評価低下:
金融機関からの融資審査などで、コンプライアンス体制が問題視され、評価が低下する可能性があります。 - 人材採用への悪影響:
企業の評判が悪化し、優秀な人材の確保が困難になる可能性があります。
建設事業者が取るべき対策|違反しないために
建設Gメンによる調査や、勧告・公表といったペナルティを避けるためには、日頃から法令遵守の意識を高め、適切な対策を講じることが不可欠です。
適正な労務費の見積もり(標準労務費の活用)
標準労務費や公共工事設計労務単価を常に意識し、必要な労務費を確保した見積もりを作成しましょう。安易な値引きは避け、根拠のある積算を心がけてください。
適正な契約の締結(見積もりの根拠を明確に)
契約書には、工事内容、請負代金、工期などを明確に記載しましょう。特に下請契約においては、見積もりの内訳(労務費、法定福利費など)をできる限り示し、合意内容を書面に残すことが重要です。
社内体制の整備(コンプライアンス体制の構築)
建設業法や下請法などの関連法規に関する社内研修を実施し、従業員のコンプライアンス意識を高めましょう。
見積もり作成・契約締結に関する社内ルールやチェック体制を整備し、担当者任せにしない仕組みを作りましょう。
内部通報制度などを設け、問題が発生した場合に早期に発見・是正できる体制を構築することも有効です。
発注者との適切なコミュニケーション
適正な労務費や工期の確保について、発注者に対して丁寧に説明し、理解を求める努力を続けましょう。標準労務費などの客観的な基準を示すことが有効です。
公正な取引で建設業の健全な発展を
建設業界における公正な取引環境の実現は、労働者の処遇改善、担い手確保、そして産業全体の持続的な発展に不可欠です。
今回のポイント再確認
- 標準労務費:適正な労務費の客観的な目安。
- 原価割れ契約禁止:不当な低価格競争を防ぐための重要なルール。
- 建設Gメン:不適切取引を監視・是正する体制。違反には厳しいペナルティも。
「建設Gメン」の存在や、勧告・公表といった措置は、一部の事業者にとってはプレッシャーに感じるかもしれません。しかし、これは建設業界全体が健全化し、公正な競争環境を実現するための重要な取り組みです。
私たち建設ドットウェブは、建設業に携わる皆様が、法令を遵守し、適正な取引を通じて事業を発展させていけるよう、情報提供や業務効率化の支援に努めてまいります。
目先の利益にとらわれず、長期的な視点でコンプライアンス体制を構築し、労働者が安心して働ける環境を整備することが、企業の信頼を高め、持続的な成長につながる道であると確信しています。