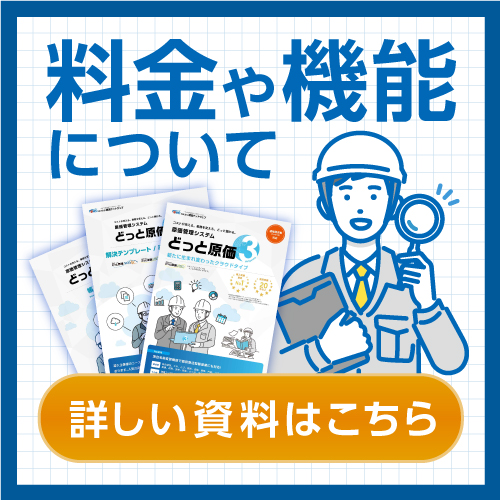【建設業法改正】労務費にしわ寄せSTOP!労働者の処遇確保・原価割れ契約禁止の新ルール

近年、建設業界では資材価格の高騰が続いており、多くの建設事業者の経営に影響を与えています。特に懸念されるのが、資材コストの上昇分が下請業者への発注価格や現場で働く方々の労務費にしわ寄せされ、結果として労働者の処遇が悪化してしまうことです。
このままでは、ただでさえ深刻な建設業の担い手不足がさらに加速し、産業全体の活力が失われかねません。
こうした事態を防ぎ、建設業で働く方々が安心して働き続けられる環境を整備するため、令和6年(2024年)に改正された「担い手3法」では、労働者の処遇確保と適正な契約関係の構築に向けた重要なルールが盛り込まれました。
この記事では、特に「労働者の処遇確保」「労務費の基準」「原価割れ契約禁止」という3つのキーワードに焦点を当て、建設業法を中心とした新しいルールとその対策について詳しく解説します。
建設業界の現状:資材価格高騰と労務費へのしわ寄せ
現在、ロシア・ウクライナ情勢や円安などを背景に、木材、鋼材、エネルギーといった建設資材の価格が依然として高い水準で推移しています。
(出典:一般財団法人建設物価調査会「建設資材物価指数グラフ」)
このような状況下で、元請負人がコスト上昇分を下請代金に適切に転嫁せず、結果的に下請業者や現場の技能労働者の労務費が圧迫されるケースが問題視されています。
問題提起:労働者の処遇低下の懸念
労務費へのしわ寄せは、単に賃金が上がらない、あるいは下がるといった問題にとどまりません。不安定な収入や将来への不安は、若手入職者の減少や、経験豊富な技能労働者の離職につながり、建設業界全体の担い手不足をさらに深刻化させる要因となります。また、適切な処遇がなされない現場では、労働者のモチベーション低下や、ひいては工事品質・安全性の低下を招くリスクも高まります。
この記事で分かること
この記事では、担い手3法改正によって強化された以下の点について解説します。
- なぜ今、労働者の処遇確保が重要なのか
- 適正な労務費の目安となる「標準労務費」とは何か
- 「原価割れ契約」や「不当に低い請負代金」に関するルールと罰則
- 建設事業者が取るべき具体的な対応策
なぜ労働者の処遇確保が必要なのか?
建設業の持続的な発展のためには、現場を支える「人」、すなわち労働者の処遇を確保することが不可欠です。
建設業の担い手不足の現状
前回の記事でも触れた通り、建設業の就業者数は減少傾向にあり、特に若年層の割合が低く高齢化が進んでいます。(出典:総務省「労働力調査」等)この人手不足の背景には、長時間労働といった労働環境の問題に加え、「給与水準が低い」「将来性が不安」といった処遇に関する問題も大きな要因として挙げられています。
処遇改善がもたらす効果
労働者の処遇を改善することは、以下のような好循環を生み出す可能性があります。
- 魅力向上・担い手確保:
適正な賃金や安定した雇用は、若者や多様な人材にとって建設業を魅力的な選択肢とし、入職促進につながります。 - 定着率向上・技術承継:
働きがいのある環境は、経験豊富な労働者の定着を促し、貴重な技術・技能の次世代への承継を円滑にします。 - モチベーション向上・生産性向上:
自身の働きが正当に評価されていると感じることは、労働者の意欲を高め、ひいては生産性の向上にも寄与します。 - 品質・安全性の向上:
適正な処遇は、労働者の責任感や集中力を高め、工事の品質確保や労働災害防止にもつながります。
「労務費の基準」とは?
今回の法改正では、適正な労務費を確保するための新たな基準として「標準労務費」の考え方が導入されました。
標準労務費とは
「標準労務費」とは、建設工事に従事する労働者の標準的な賃金水準を示すものです。国土交通大臣が、公共工事設計労務単価(公共工事の予定価格を積算するための基準単価で、職種ごとに定められている。)などを参考に作成し、建設業者や発注者に対して、この水準の労務費を確保するよう勧告できるようになります。その目的は、労務費のダンピング(不当な値引き)を防ぎ、労働者に適正な賃金が支払われるようにすることです。
標準労務費の算出方法
具体的な算出方法の詳細は今後のガイドライン等で示されますが、公共工事設計労務単価をベースとしつつ、社会保険料の事業主負担分や、各地域の賃金実態なども考慮される見込みです。
標準労務費の活用方法
- 見積もり作成の目安:
下請業者が元請業者に見積もりを提出する際や、元請業者が発注者に見積もりを提出する際に、標準労務費を参考に適正な労務費を計上することが求められます。 - 契約交渉の根拠:
価格交渉において、「標準労務費に基づいた適正な労務費である」ことを説明する根拠として活用できます。国土交通省が作成・勧告する基準であるため、客観的な説得力を持つことが期待されます。 - 標準見積書の活用:
国土交通省が推奨する「標準見積書」には、労務費や法定福利費などを内訳として明示する欄があります。標準労務費を参考に、これらの項目を適切に記載し提出することが重要です。
「原価割れ契約禁止」のルール
建設業法では、以前から「不当に低い請負代金の禁止」(第19条の3)が定められていますが、今回の改正で、労働者の処遇確保の観点から、その運用が強化されます。
原価割れ契約とは
「原価割れ契約」とは、工事を完成するために通常必要とされる費用(労務費、材料費、経費など)を下回る金額で請負契約を締結することです。このような契約は、下請業者にしわ寄せが及び、労働者の賃金不払いや安全対策の不備、手抜き工事などを引き起こす原因となります。
建設業法における原価割れ契約の扱い
建設業法は、明確に「原価割れ契約」という言葉で禁止しているわけではありませんが、「不当に低い請負代金」での契約締結を禁止しています。今回の改正では、この規制の実効性を高めるための措置が講じられました。
見積内訳の明示義務
元請負人が下請負人に見積もりを依頼する際には、工事の工程ごとの作業量や、それに対応する労務費、材料費、経費などの内訳を可能な限り明示することが求められます。これにより、下請業者はより正確な見積もりを作成しやすくなり、不当な値引き要求を防ぐことにつながります。
不当に低い請負代金の禁止
請負代金の額が、その工事の「通常の原価」を著しく下回る場合に、「不当に低い請負代金」と判断される可能性があります。今回の改正では、特に労務費相当額について、元請負人に著しく低い見積もりや契約を行わないよう配慮する努力義務が課せられました。標準労務費がこの「通常の原価」を判断する上での一つの目安となり得ます。
違反した場合の罰則
標準労務費を著しく下回るなど、不当に低い請負代金での契約が疑われる場合、国土交通大臣や都道府県知事は、元請負人に対して必要な勧告を行うことができます。勧告に従わない場合は、その事実が公表される可能性があります。公表されれば、企業の信用失墜につながる恐れがあります。
不当に低い請負代金での契約が悪質であると判断された場合や、下請法違反など他の法令違反も伴う場合には、建設業法に基づく監督処分(指示処分、営業停止処分など)の対象となる可能性もあります。
建設事業者が取るべき対応
労働者の処遇を確保し、法令を遵守するためには、建設事業者は以下の対応を取ることが求められます。
適正な見積もりの作成
標準労務費や公共工事設計労務単価を参考に、必要な労務費を正確に算出し、見積もりに反映させましょう。
材料費、経費なども含め、根拠のある積算を行い、見積書には可能な限り内訳(特に労務費、法定福利費)を明示しましょう。
国土交通省の「標準見積書」を活用することも有効です。
契約交渉
発注者や元請負人との価格交渉においては、標準労務費や積算根拠を示し、労務費確保の重要性を粘り強く説明しましょう。
不当に低い金額での契約を強要された場合は、安易に受け入れず、建設業法違反の可能性があることを指摘することも必要です。
社内体制の整備
適正な見積もり作成ルール、契約締結に関するチェック体制を社内で整備しましょう。
労務管理を徹底し、労働時間や賃金の支払い状況を正確に把握しましょう。
社員(特に営業・積算担当者)に対して、法改正の内容や適正な見積もりの重要性について教育・周知を図りましょう。
持続可能な建設業のために
今回の法改正は、建設業界が長年抱えてきた課題に正面から向き合い、未来に向けて変革を進めるための重要な一歩です。
今回のポイント再確認
- 労働者の処遇確保:建設業の未来を支える「人」を守り育てるための最重要課題。
- 労務費の基準(標準労務費):適正な賃金水準を確保するための客観的な目安。
- 原価割れ契約禁止(不当に低い請負代金の禁止):公正な取引関係を構築し、しわ寄せを防ぐためのルール。
適正な労務費を確保し、労働者の処遇を改善することは、短期的にはコスト増につながるかもしれません。しかし、それは未来への投資です。働きがいのある環境を提供することで、優秀な人材が集まり、定着し、技術力が向上し、ひいては企業の競争力強化と建設業界全体の持続的な発展につながります。
私たち建設ドットウェブは、建設業に携わる皆様が、これらの新しいルールに適切に対応し、事業を成長させていけるよう、情報提供やシステム導入支援などを通じてサポートしてまいります。
法令遵守はもちろんのこと、建設業で働くすべての人々が誇りを持って活躍できる産業を目指し、共に取り組んでいきましょう。