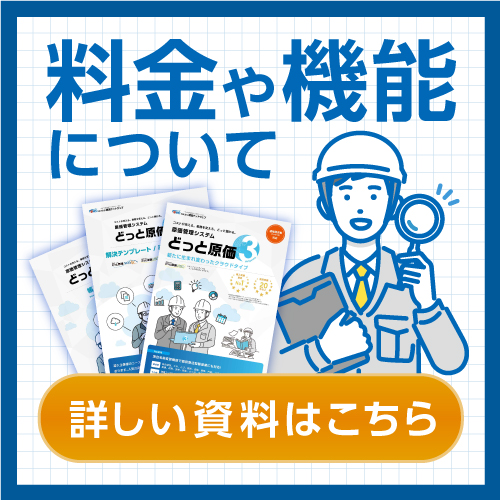【令和6年改正】第三次・担い手3法改正の全貌を解説!背景・目的・実務への影響は?
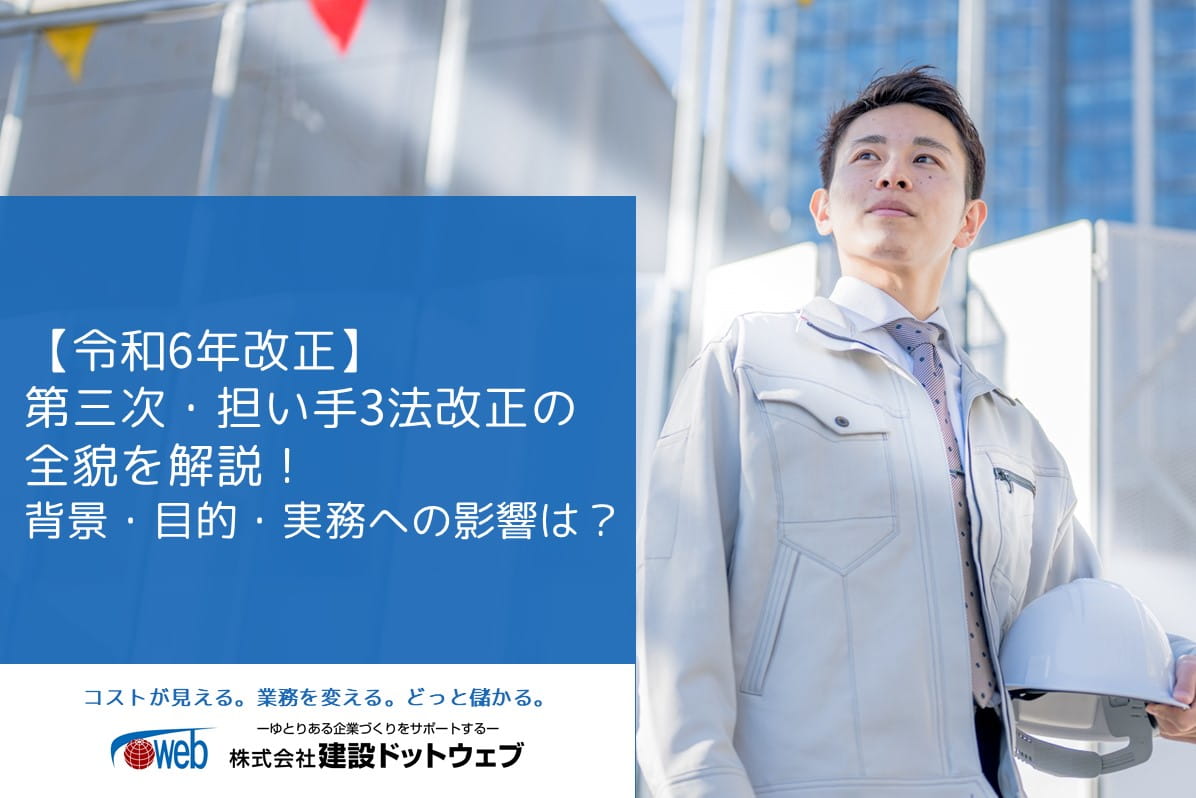
近年、建設業界は深刻な人手不足や働き手の高齢化、長時間労働といった多くの課題に直面しています。これらの課題は、建設業の持続可能性を脅かすだけでなく、社会インフラの維持・更新にも影響を及ぼしかねません。
こうした状況を打開し、建設業が将来にわたって魅力ある産業であり続けるために、国はこれまでも様々な対策を講じてきました。そして、令和6年(2024年)には、建設業の担い手確保と生産性向上をさらに推し進めるため、「担い手3法」と呼ばれる重要な法律の一体的改正が行われました。
この改正は、建設業に携わるすべての事業者にとって、今後の事業運営に大きな影響を与える可能性があります。しかし、「具体的に何が変わるのか?」「自社にはどんな影響があるのか?」「何を準備すればいいのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業法・入札契約適正化法(入契法)・公共工事品質確保促進法(品確法)からなる「第三次・担い手3法」改正について、その背景から具体的な改正内容、企業への影響、そして取るべき対応まで、網羅的に分かりやすく解説します。
目次
建設業界の現状と課題
現在の建設業界は、以下のような厳しい課題に直面しています。
- 深刻な人手不足と高齢化:若年層の入職者減少と、就業者の高齢化が同時に進行しています。国土交通省のデータによると、建設技能労働者の約3割が55歳以上である一方、29歳以下の割合は約1割にとどまっています。(※最新のデータを挿入・出典明記推奨)このままでは、将来的に技術・技能の承継が困難になる恐れがあります。
- 長時間労働の常態化:他産業と比較して、建設業の労働時間は依然として長い傾向にあります。週休2日の確保も十分に進んでおらず、若者や女性にとって働きがいのある環境とは言いがたい状況です。2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用されましたが、その遵守も大きな課題となっています。
- 生産性の伸び悩み:現場作業の多くが人手に頼っており、ICT(情報通信技術)などの導入が進んでいない中小企業も少なくありません。資材価格の高騰も、企業の収益性を圧迫する要因となっています。
「担い手3法」改正の必要性
これらの課題を放置すれば、建設業の担い手はますます減少し、必要なインフラ整備や災害対応に支障をきたす恐れがあります。また、労働環境の悪化は、労働災害のリスクを高め、企業の持続可能性をも損ないかねません。
そこで、建設業の働き方改革を推進し、生産性を向上させ、多様な人材が活躍できる魅力ある産業へと転換していくことが急務となっています。今回の「第三次・担い手3法」改正は、こうした喫緊の課題に対応し、建設業の持続的な発展を図るために不可欠な取り組みなのです。
この記事で分かること
この記事を読むことで、以下の内容を理解できます。
- 「担い手3法」とは何か、これまでの改正経緯
- 今回の「第三次・担い手3法」改正の背景と目的
- 建設業法、入契法、品確法の具体的な改正内容
- 改正が建設業界や企業に与える影響(メリット・デメリット)
- 建設事業者が取るべき具体的な対応策
担い手3法とは?(過去の改正経緯のおさらい)
今回の改正内容を理解するために、まずは「担い手3法」の基本的な役割と、これまでの改正の流れをおさらいしましょう。
担い手3法(建設業法、入契法、品確法)の概要と役割
「担い手3法」とは、以下の3つの法律の総称です。これらは相互に連携し、建設工事の適正な施工、発注者・受注者の保護、そして建設業の健全な発展を支えています。
- 建設業法
建設業者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化などを目的とし、建設業を営む上での基本的なルールを定めています。(許可制度、技術者制度、下請保護など) - 入札契約適正化法(入契法)
公共工事の入札・契約手続きの透明性・公正性を確保し、不正行為を防止することを目的としています。(入札情報の公表、談合防止措置など) - 公共工事品質確保促進法(品確法)
公共工事の品質を将来にわたって確保するため、発注者の責務や多様な入札契約方式の活用などを定めています。(価格と品質で総合的に評価する方式の導入促進など)
第一次・第二次改正のポイントと成果、残された課題
担い手3法は、時代の変化や建設業が抱える課題に対応するため、これまでも改正が重ねられてきました。
- 第一次改正(平成26年):
主に品確法が改正され、公共工事の品質確保と担い手の中長期的な育成・確保が基本理念として明確化されました。「歩切り」(予定価格を下回る額で入札参加を強要すること)の根絶などが盛り込まれました。 - 第二次改正(令和元年):
建設業法と品確法が改正され、働き方改革の促進(著しく短い工期の禁止など)、生産性向上(ICT活用促進など)、災害時の対応力強化などが図られました。
これらの改正により、一定の成果は見られたものの、依然として担い手不足や長時間労働といった課題は解消されていません。特に、資材価格の高騰に伴う労務費へのしわ寄せや、時間外労働の上限規制への対応など、新たな課題も顕在化しています。
第三次・担い手3法改正(令和6年改正)の全体像
このような背景を踏まえ、令和6年(2024年)に「第三次・担い手3法」の一体的改正が行われました。ここでは、その全体像を見ていきましょう。
改正の目的
今回の改正は、以下の3つを大きな柱としています。
- 担い手の確保・育成:
働き方改革の推進(時間外労働規制への対応、週休2日の確保)
処遇改善(適正な賃金水準の確保)
技術者・技能者の育成強化 - 生産性の向上:
施工時期の平準化
資材高騰等への適切な対応
建設DX(デジタル技術の活用)の推進 - 持続可能な事業環境の整備:
適正な価格での契約締結の促進
地域建設業の役割と持続可能性の確保
改正のポイント
上記目的を達成するため、各法律で以下のような改正が行われます。(主なポイントを抜粋。詳細は後述)
- 建設業法:
働き方改革の促進(時間外労働規制遵守、中央建設業審議会による工期基準作成)
処遇改善(標準労務費の勧告、下請代金における労務費相当額への配慮)
生産性向上(特定専門工事における元下間の合意による再下請負の制限緩和)
技術者制度の見直し(主任技術者の配置要件緩和) - 入契法:
発注関係事務の運用に関する基準作成(労務費等の反映、工期の適正化)
公共工事の施工体制に関する情報のデジタル化 - 品確法:
発注者の責務の明確化(働き方改革・生産性向上への配慮)
多様な入札契約方式の活用促進(最新技術の活用、災害対応など)
施工時期の平準化の推進強化
改正スケジュール
公布日:令和6年6月14日
施行日:一部を除き、公布日から2年以内(具体的な施行日は政令で定められます)。時間外労働規制に関する工期基準作成などは公布日から6ヶ月以内。
※施行日は改正項目によって異なるため、最新情報を国土交通省のウェブサイト等でご確認ください。
各法律の改正内容詳細解説
ここからは、各法律の改正内容について、もう少し詳しく見ていきましょう。
建設業法の改正点
建設業を営む上で最も基本的なルールを定める建設業法では、特に働き方改革、処遇改善、生産性向上に関する重要な改正が行われます。
主任技術者・監理技術者の配置要件緩和
特定の条件を満たす下請工事について、一定の能力を有する主任技術者(例:1級技士補など)であれば、複数の工事現場を兼任できるようになります。また、特例監理技術者の配置が可能な工事の範囲も拡大されます。
- メリット:限られた技術者を有効活用でき、技術者不足の緩和につながります。
- デメリット・注意点:技術者の負担増につながる可能性もあります。適切な現場管理体制の構築や、技術者の能力・経験に応じた配置が重要です。
下請け代金の支払いに関する規制強化
元請負人に対し、下請負人と契約する際に、労務費相当額について、著しく低い見積もりや契約をしないよう配慮する努力義務が課せられます。また、見積もり依頼時に労務費や資材費の内訳を明らかにすることも求められます。標準労務費の勧告制度も創設されます。
- メリット:下請業者への不当なしわ寄せを防ぎ、労働者の処遇改善につながることが期待されます。
- 罰則・対策:著しく低い請負代金での契約は、建設業法違反(不当に低い請負代金の禁止)として勧告・公表の対象となる可能性があります。元請業者は、標準労務費などを参考に、適正な労務費を見積もり・契約に反映させる必要があります。下請業者は、標準見積書を活用し、根拠のある見積もりを提示することが重要です。
その他の改正点
- 時間外労働規制に関する工期基準作成:
中央建設業審議会が、時間外労働規制を遵守できるような適正な工期に関する基準を作成し、勧告します。 - 特定専門工事における再下請負制限の緩和:
特定専門工事において、元請負人と下請負人が合意した場合、一定の条件下で再下請負が可能になります。(生産性向上目的) - 社会保険加入の徹底:
下請指導ガイドライン等により、社会保険未加入業者への対策が強化されます。
入契法の改正点
公共工事の入札・契約ルールを定める入契法では、主に適正な価格での契約と施工時期の平準化に関する改正が行われます。
- 発注関係事務の運用基準作成:
国が、公共工事の発注関係事務(予定価格の設定、低入札価格調査基準の設定など)に関する基準を作成・公表します。この基準には、労務費、資材費等の適切な反映や、適正な工期設定に関する事項が含まれます。 - 低入札価格調査基準等の引き上げ:
労務費上昇などを踏まえ、低入札価格調査基準や失格基準の引き上げが検討されます。 - 公共工事の施工体制に関する情報のデジタル化:
施工体制台帳などの情報をデジタル化し、関係者間で共有する仕組みの構築が推進されます。
品確法の改正点
公共工事の品質確保を目指す品確法では、発注者の責務強化や多様な入札契約方式の活用促進などが盛り込まれます。
- 発注者の責務の明確化:
発注者に対し、働き方改革(週休2日、適正工期など)や生産性向上(ICT活用など)に配慮した発注を行う責務が明確化されます。 - 多様な入札契約方式の活用促進:
最新技術を活用する工事や、災害時の緊急工事など、工事の特性に応じた多様な入札契約方式(技術提案評価型など)の活用が促進されます。 - 施工時期の平準化の推進強化:
発注者に対し、年度末に集中しがちな工事の施工時期を平準化するための計画作成・公表が義務付けられます。
その他関連法規の改正点
今回の担い手3法改正と直接連動するものではありませんが、建設業に関連する他の法規(例:建設リサイクル法、労働安全衛生法など)の動向にも注意が必要です。
改正による建設業界・企業への影響
今回の法改正は、建設業界全体、そして個々の企業にどのような影響を与えるのでしょうか。
メリット
労働環境の改善:適正な工期設定や労務費の確保により、長時間労働の是正や賃金水準の向上が期待され、担い手確保・定着につながります。
- 生産性の向上:
技術者配置の効率化やICT活用の推進により、生産性の向上が期待されます。 - 受注機会の確保(下請業者):
適正な価格での契約が促進されることで、下請業者の経営安定化につながります。 - 品質の向上:
適正な工期・費用が確保されることで、工事品質の向上が期待されます。
デメリット・注意点
- コスト増加の可能性:
適正な労務費や安全衛生経費の確保、ICT導入などにより、一時的にコストが増加する可能性があります。 - 新たな義務への対応:
見積もり内訳の明示、工期基準の遵守など、新たな義務に対応するための体制整備が必要です。 - 手続きの変更:
入札・契約手続きや、技術者の配置ルールなどが変更されるため、最新情報の確認と対応が必要です。 - 発注者側の理解:
特に民間工事においては、発注者側に法改正の趣旨を理解してもらい、適正な価格・工期での契約に協力してもらう必要があります。
建設事業者が取るべき対応
今回の法改正に適切に対応し、これを成長の機会とするためには、以下の準備を進めることが重要です。
情報収集
最新情報のキャッチアップ:国土交通省のウェブサイトや、建設業関連団体(全国建設業協会、建設業振興基金など)が発信する情報を定期的に確認しましょう。
- セミナー等への参加:
国や業界団体、民間企業が開催するセミナーに参加し、専門家による解説を聞くことも有効です。
社内体制の整備
- 就業規則の見直し:
時間外労働の上限規制や、賃金規定(標準労務費を参考にするなど)について、必要に応じて見直しを行いましょう。 - 業務フローの見直し:
見積もり作成プロセス(労務費等の内訳明示)、契約管理、技術者配置などの業務フローを見直し、法改正に対応できるように整備しましょう。 - 社員への周知徹底:
改正内容と自社の対応方針について、社員(特に営業担当、現場担当、事務担当)に周知し、理解を促しましょう。
専門家への相談
法改正の内容や実務への影響について不明な点があれば、顧問弁護士や社会保険労務士、建設業に詳しいコンサルタントなどの専門家に相談することを検討しましょう。
改正をチャンスに変えるために
今回の「第三次・担い手3法」改正は、建設業界が抱える構造的な課題に本格的に取り組み、持続可能な産業へと変革していくための重要な一歩です。
改正のポイント再確認
- 働き方改革の加速:時間外労働規制遵守、適正工期
- 処遇改善:標準労務費、適正な下請代金
- 生産性向上:技術者配置緩和、ICT活用促進
- 適正な契約:発注者の責務明確化、施工時期平準化
メッセージ
この改正は、一部の事業者にとっては負担増と感じられる側面もあるかもしれません。しかし、長期的に見れば、労働環境の改善や生産性向上は、企業の競争力強化、ひいては建設業界全体の魅力向上につながります。
私たち建設ドットウェブは、建設業に携わる皆様が、この変化を前向きに捉え、適切に対応できるよう、引き続き最新の情報提供や、業務効率化を支援するソリューションの提供に努めてまいります。
今回の法改正を、単なる規制強化と捉えるのではなく、自社の働き方や生産性を見直し、より良い企業へと成長するためのチャンスと捉え、積極的に取り組んでいきましょう。