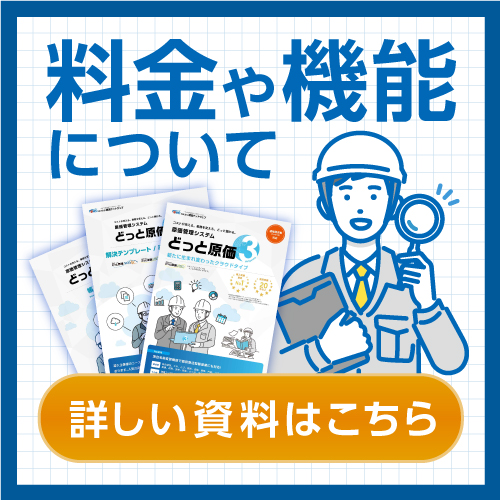公共工事の利益率を向上させる計算方法と実例

工事の受注数や売上高を伸ばすことに注力するあまり、肝心の利益率管理がおろそかになっていませんか?この記事では、公共工事における利益率向上のための具体的な計算方法と、実践的な取り組み方を解説します。
公共工事における利益率の重要性
公共工事を請け負う建設業者にとって、利益率の管理は経営の安定と持続的な事業運営のために欠かせません。ここでは、建設業における一般的な利益率の範囲や、事業規模や受注内容による利益率の変動について解説します。
建設業の一般的な利益率の範囲
建設業における一般的な利益率は、18%から25%の範囲内であると言われています。この利益率の幅は、建設業者の事業規模や、元請けか下請けかの立場、そして民間工事と公共工事の種別によって変動します。
例えば、大手建設業者の場合、事業規模が大きいため、利益率は比較的低くても安定した利益を確保しやすい傾向にあります。一方、中小規模の建設業者は、事業規模が小さいため、利益率を高めに設定しないと十分な利益を確保しにくい状況があります。
事業規模や受注内容による利益率の変動
建設業者の利益率は、事業規模だけでなく、受注する工事の内容によっても大きく変動します。公共工事の場合、入札による価格競争が激しいため、利益率は民間工事と比べて低くなる傾向にあります。
また、元請けと下請けでは、利益率に差が生じることが一般的です。元請けは工事全体の管理や調整に責任を持つため、それに見合った利益を確保する必要があります。一方、下請けは元請けから受注した工事を実施するため、利益率は元請けよりも低くなることが多いのです。
売上増加だけでは不十分な経営安定化の理由
建設業者の中には、売上を増加させることだけに注力し、利益率の管理を怠る傾向があります。しかし、売上が増加しても、利益率が低ければ、十分な利益を確保することはできません。
建設業では、工事の進行に伴って、資材の調達や労務費の支払いなど、多くの支出が発生します。売上が増えても、支出が売上以上に増加してしまうと、利益は減少してしまうのです。したがって、売上増加と同時に、適正な利益率の維持が重要となります。
適正利益の確保による持続的な事業運営の必要性
建設業者が持続的に事業を運営するためには、適正な利益を確保することが不可欠です。利益は、事業の維持・発展に必要な設備投資や人材育成、技術開発などに投資される重要な資金源となります。
また、工事の品質を維持し、安全な施工を行うためにも、適正な利益の確保が必要です。利益率が低すぎると、品質の維持や安全対策にかかる費用を削減せざるを得なくなり、結果として工事の質の低下や事故のリスクが高まってしまいます。
利益率向上のための具体的な計算方法
ここでは、利益率を高めるための具体的な計算方法について解説します。
粗利益と利益率の計算式
利益率を向上させるためには、まず粗利益と利益率の計算方法を正しく理解することが重要です。粗利益は、完成工事高から工事原価を差し引いて算出します。一方、利益率は、粗利益を売上高で割り、100を掛けることで求められます。
これらの計算式を用いて、自社の工事における粗利益と利益率を正確に把握することが、利益率向上への第一歩となります。計算結果を分析し、利益率が低い工事については、原因を究明し、改善策を講じることが必要です。
適切な見積金額の設定方法
利益率を向上させるには、適切な見積金額の設定が欠かせません。見積金額は、工事原価と経費の合計に、目標とする利益を上乗せして算出します。この際、工事の規模や難易度、自社の技術力などを考慮し、適正な利益率を設定することが重要です。
また、見積金額の設定に際しては、過去の類似工事の実績データを参考にすることも有効です。過去の工事で得られた教訓を活かし、適切な見積金額を設定することで、利益率の向上が期待できます。
社内見積作成基準の統一の重要性
利益率を安定的に向上させるためには、社内の見積作成基準を統一することが重要です。見積作成基準が統一されていない場合、担当者によって見積金額にばらつきが生じ、利益率の低下を招く恐れがあります。
社内見積作成基準の統一に際しては、工事原価の算出方法や、経費の計上基準、利益率の設定基準などを明確に定める必要があります。また、基準の運用状況を定期的に確認し、必要に応じて改善を図ることも重要です。
工事原価の適切な管理手法
利益率の向上には、工事原価の適切な管理が欠かせません。工事原価の管理においては、資材費、労務費、外注費などの各費目について、計画値と実績値を比較し、差異の原因を分析することが重要です。
また、工事の進捗に応じて、原価の発生状況を定期的に確認し、必要に応じて対策を講じることも必要です。原価管理のためには、現場管理者と経理担当者の緊密な連携が不可欠であり、情報共有の仕組みづくりが重要となります。
利益率改善に向けた実践的なポイント
ここでは、利益率向上のための実践的なポイントを解説します。
赤字受注の回避による利益確保
利益率を改善するための第一歩は、赤字受注を絶対に避けることです。赤字受注は、利益だけでなく、会社の信用や従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。適切な見積もりを作成し、利益率を考慮した上で受注可否を判断することが重要です。
見積もりの作成に際しては、過去の類似工事の実績データを参考にし、工事の規模や難易度、自社の技術力などを考慮して、適正な利益率を設定しましょう。受注前に十分な検討を行い、赤字受注のリスクを最小限に抑えることが、利益率改善への第一歩となります。
品質に関わるコスト以外での削減余地の探索
利益率を改善するためには、工事原価の削減が欠かせません。ただし、品質に直接関わるコストを安易に削減することは避けなければなりません。品質の低下は、顧客満足度の低下や手直し工事の発生など、長期的には利益率の悪化につながる恐れがあるからです。
そこで重要となるのが、品質に関わらないコストでの削減余地の探索です。例えば、資材の調達方法の見直しや、施工手順の効率化、余剰人員の削減などが考えられます。現場の状況を詳細に分析し、無駄を省くことで、利益率の改善が期待できます。
リアルタイムでの原価把握と管理の実施
利益率を安定的に改善するためには、工事の進行に合わせて、リアルタイムで原価を把握し、管理することが重要です。工事の進捗に応じて原価の発生状況を定期的に確認し、計画値と実績値の差異を分析することで、早期に問題を発見し、対策を講じることができます。
原価管理のデジタル化は、リアルタイムでの原価把握を可能にする有効な手段です。クラウドサービスなどを活用することで、現場と経理部門の情報共有が円滑になり、より精緻な原価管理が実現します。デジタルツールを効果的に活用し、リアルタイムでの原価管理を実践することが、利益率改善への近道となるでしょう。
受注前の実行予算作成による利益シミュレーション
利益率を改善するためには、受注前の段階で、適切な利益シミュレーションを行うことが重要です。実行予算を作成し、工事原価と経費を詳細に見積もった上で、目標とする利益率を達成するための受注金額を算出します。
この利益シミュレーションを通じて、受注可否の判断や、価格交渉の指針を得ることができます。また、受注後も実行予算を基に原価管理を行うことで、利益率の改善に役立てることができます。受注前の入念な利益シミュレーションは、利益率改善のための重要なステップといえるでしょう。
原価管理のデジタル化による利益率向上
近年、原価管理のデジタル化が進み、これを活用することで利益率の改善が期待できます。ここでは、原価管理のデジタル化による利益率向上について解説します。
リアルタイムでの原価と利益の可視化
原価管理のデジタル化の最大の利点は、リアルタイムでの原価と利益の可視化が可能になることです。従来の手作業による原価管理では、データの収集や集計に時間がかかり、意思決定をすぐに行うことが難しいという課題がありました。しかし、デジタルツールを活用することで、工事の進捗に合わせて原価データを自動的に収集・集計し、リアルタイムで原価と利益を可視化することができます。
これにより、工事の進行中に原価の異常値を早期に発見し、迅速に対策を講じることが可能となります。また、利益率の推移をリアルタイムで把握することで、工事の採算性を常に意識した管理が実現します。リアルタイムでの原価と利益の可視化は、利益率向上のための強力な武器となるでしょう。
見積から原価管理までの一元管理の実現
原価管理のデジタル化のもう一つの大きな利点は、見積から原価管理までの一元管理が実現できることです。従来、見積作成と原価管理は別々のシステムで行われることが多く、データの連携や整合性の確保が困難という課題がありました。しかし、デジタルツールを活用することで、見積データと実際の原価データを同一のシステム上で管理することが可能となります。
見積と原価管理の一元化により、見積精度の向上と原価管理の効率化が図られます。見積作成時に過去の類似工事の原価データを参照することで、より現実的な見積もりが可能となります。また、見積データと実際の原価データを常に比較分析することで、原価超過の早期発見と対策が可能となります。見積から原価管理までの一元管理は、利益率向上に直結する重要な取り組みといえるでしょう。
入札や価格交渉時の判断材料としての活用
原価管理のデジタル化は、入札や価格交渉時の判断材料としても活用できます。デジタルツールを用いて過去の類似工事の原価データを分析することで、適正な利益率を確保するための最低受注金額を算出することができます。この情報を基に、入札価格の設定や価格交渉の方針を決定することで、赤字受注のリスクを最小限に抑えることが可能となります。
また、受注前の段階で、デジタルツールを用いて詳細な実行予算を作成し、利益シミュレーションを行うことも有効です。これにより、受注可否の判断や価格交渉の指針を得ることができます。入札や価格交渉時の判断材料としてデジタルツールを活用することで、利益率の向上に大きく寄与することができるでしょう。
進行中の工事の収支予測の容易化
原価管理のデジタル化は、進行中の工事の収支予測を容易にするという利点もあります。デジタルツールを用いて、工事の進捗に合わせて原価データを収集・分析することで、最終的な利益率を高い精度で予測することが可能となります。この情報を基に、工事の採算性を常に意識した管理を行うことができます。
収支予測の精度が高まることで、利益率の低下が予想される場合には、早期に対策を講じることが可能となります。例えば、原価削減の余地を探るために施工方法の見直しを行ったり、追加の資金調達を検討したりするなどの対応が考えられます。進行中の工事の収支予測を容易にすることで、利益率の安定的な確保が期待できます。
まとめ
公共工事における利益率の向上は、建設業者の経営安定と持続的な事業運営のために欠かせません。その実現のためには、適正な利益率の重要性を認識し、具体的な計算方法や実践的なポイントを押さえることが求められます。見積金額の適切な設定、社内基準の統一、工事原価の管理など、利益率を意識した取り組みが重要です。さらに、原価管理のデジタル化を進めることで、リアルタイムでの可視化や一元管理、データ活用による判断の精度向上など、利益率改善に役立てることができるでしょう。建設業者の皆様におかれましては、これらの手法を実践し、公共工事における利益率の着実な向上を目指していただきたいと思います。